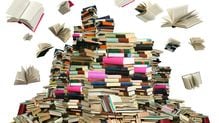※本稿は、増田晶文『蔦屋重三郎 江戸の反骨メディア王』(新潮選書)の一部を再編集したものです。
歌麿は18歳前後で石燕一門として絵師デビュー
歌麿の画が初めて世に出たのは明和7(1770)年だった。
蔦屋重三郎(蔦重)が21歳になって、ようよう吉原細見を売ろうかという頃、歌麿は歳旦絵入俳諧『ちよのはる』に挿画を残した。これは正月の会で披露する俳諧を集めた俳書で鳥山石燕一門が中心となり画を担当したもの。『ちよのはる』収録の茄子の画には「少年石要画」の署名があり、これが歌麿デビュー作とされる。
おかげで、ようやく歌麿の来歴が具体的な形をもって浮かびあがってきた。まず歌麿が石燕の弟子だったこと。石燕は俳諧に深く親しみ、その道では東柳窓燕志の門下とされる。絵は狩野周信、玉燕から学んだ。石燕には「石」か「燕」の字をとった弟子が多く、歌麿の「石要」もその伝にならっている。また、後年の歌麿の武者絵『関羽』に「零陵洞門人哥麻呂画」とあり、零陵洞が石燕の号なので師弟関係にあることは判然としている。
「子ども時代の歌麿」を石燕が書き残している
そして話は18年後の天明8年に飛ぶのだが――蔦重が歌麿に卓抜の写生術を発揮させた『画本虫撰』に石燕は跋文を寄せているので意訳してみよう。
「子どもだった歌麿は秋津虫(トンボ)を繫ぎ、はたはた(バッタ)、蟋蟀(コオロギ)などを手の上に乗せてあそんでいた」

歌麿が何歳で石燕に入門したのかはわからぬが、虫遊びに夢中になるのだから10歳くらいまでのことか。しかし、石燕はいかなる理由で幼子を弟子に迎えたのか、それもまた詳らかにはなっていない。おかげで歌麿が石燕の庶子あるいは養子だったという説がある。
かくいう石燕は狩野派の絵師だったが本絵より卑俗な世界で活躍した。ことに妖怪画は有名で『画図百鬼夜行』『今昔画図続百鬼』はじめ数々の版本が現存している。石燕の描く妖怪画を一瞥すれば、『ゲゲゲの鬼太郎』の水木しげるに大きな影響を与えているのは明白。その意味で今日の私たちが抱く妖怪のビジュアルイメージは石燕に負うところが大きい。