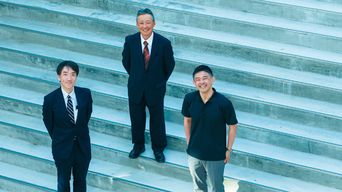※本稿は、フレデリック・クレインス『戦国武家の死生観』(幻冬舎新書)の一部を再編集したものです。
明智光秀が最も信頼していた武将に届いた衝撃の知らせ
天正10(1582)年6月3日――。
早朝の光が差し込む陣屋で、細川忠興は出陣の準備に忙殺されていた。羽柴秀吉に加勢するため、明智光秀や池田信輝らとともに備中へ向かうことになっていたのである。
備中高松城を水攻めにしていた秀吉の要請を受け、織田信長は光秀らに出陣を命じ、みずからも軍勢を率いて毛利氏との決戦に臨もうとしていた。
すでに出発した細川軍の先陣が宮津城外の犬堂まで達したころ、愛宕下坊の幸朝僧正が手配した飛脚が広間に駆け込んできた。息を切らしながら文箱を差し出した男の足は、泥にまみれていた。
文箱から取り出された書状には、衝撃的な内容が記されていた。
「昨二日、信長公ご父子は明智日向守殿の軍勢に襲われ、本能寺と二条御所にてお腹を召され……」
予想もしなかった知らせに忠興は驚愕し、取り急ぎ出陣を取りやめた。そして、先陣に城へ引き返すよう指示した。すると、間もなく、光秀の使者として沼田権之助が忠興のもとを訪れた。
親子ともども髷を落とした
「信長公ご父子には、腹を切っていただきました。このうえは急ぎ軍勢を率いて、ご上洛いただきたい。ちょうど播磨が空いておりますので、差し上げます」
使者が光秀の言葉を伝えると、忠興とともに口上を聞いていた父の藤孝が静かに口を開いた。
「私は上様(信長)から大きなご恩をいただいた。出家しようと思う。だが、おまえは明智殿と婿舅の間柄だ。判断は任せる」
しかし、忠興の気持ちはすでに決まっていたとみえて、ひと言も発することなく髻を落とし、父と同心であることを示した。そして、その場で使者を成敗すると言ったが、藤孝に制止されて思いとどまった。
以上の場面は、宇土細川家で編纂された「忠興公譜」に記録されている、本能寺の変が細川家に伝えられた際の様子です。
宇土細川家は、忠興の四男立孝の流れをくむ熊本藩の支藩で、「忠興公譜」は本家の事績を記録するために編纂された「細川家譜」の一部として、寛文8(1668)年から延宝年間(1673年から81年)までに作成されました。