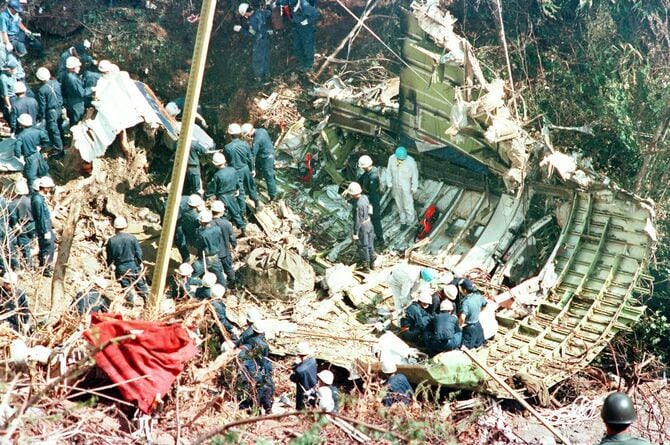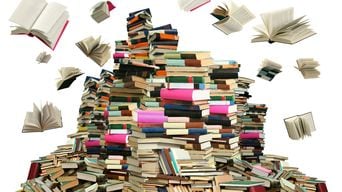※本稿は、米田憲司『日航123便事故 40年目の真実 御巣鷹の謎を追う 最終章』(宝島社)の一部を再編集したものです。
思い通りに操縦できず、激しく揺れる機体
123便は相模湾上空で垂直尾翼の大半を失い、油圧系統の配管が裁断されて徐々に思うように操縦できなくなっていった。乗員は原因についていろいろ考えているはずだが、音声記録にはなぜかそういう会話はない。
焼津市を通過したあたりから次第にダッチロール(左右の揺れ)が激しくなり、右に60度、ついで左に50度も傾いた。機長は「バンク(傾き)をそんなにとるな」と注意するが、すでにパイロットの思い通りの操縦はできなくなっていたと推察される。ダッチロールによる横揺れで、風きり音が笛のように不気味に聞こえてくる。
フゴイド(機首の上下運動)が加わり、15度から20度も機首が上向き、今度は10度から15度も機首下げの状態を繰り返す。上昇、降下、旋回もできず、東京航空交通管制部(埼玉・所沢市)に要求した大島経由で羽田空港への帰還はできない状態になっていく。123便は右に大きく旋回し、北の富士山の方向へと飛行していく。
乗客は「パパは本当に残念だ」と書き残す
操縦室音声記録には録音されていないが、この時点の18時30分頃に客室では大阪・箕面市の谷口正勝さんが「まち子、子供よろしく」と機内に備えてある紙袋に遺書を書いている。
横浜市の吉村一男さんは会社の書類に「残された二人の子供をよろしく」と書いている。
神奈川・藤沢市の河口博次さんも「マリコ、津慶、知代子、どうか仲良くがんばってママをたすけて下さい。パパは本当に残念だ。きっと助かるまい……ママこんなことになるとは残念だ。さようなら……」と手帳に書いている。
操縦室では、機体左右のエンジンの推力調整の操作にも次第に慣れ、機体も安定していく。この頃、乗員の会話では酸素マスクをつけるかどうかのやりとりもあるが、酸素マスクをつけないまま最後まで操縦を続けていく。酸素マスクをつけていないと思える理由は、乗員の声がくぐもった声になっていないからだ。