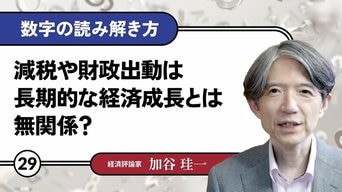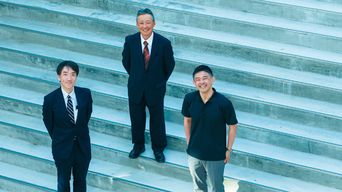※本稿は、林英一『南方抑留』(新潮選書)の一部を再編集したものです。
東京帝国大学哲学科を出た青年がみた戦場
1920年、富山県生まれの林禮二は、1941年に東京帝国大学文学部西洋哲学科を繰り上げ卒業した後、出版文化協会に職を得た。しかしわずか1カ月で兵役につくことになり、1942年2月に金沢の砲兵連隊に入営し、見習士官となり、翌年5月に南方に派遣される。
林が内地から持参したノートには、箱根丸に乗船して門司を出たときの心境が、「愈愈祖国を後にする。懐旧の念と俱に未だ見ぬ南の国に思ひは馳せる」(1943年5月1日)と綴られている。2日後、船が澎湖諸島に入り、「もう常夏の国に来たのだ、暑さも厳しい」(同年5月3日)と南国の洗礼を浴びたが、「初めて見る南の国、青い青い海」(同年5月4日)に目を輝かせた。
しかし生来「引込み思案」(1946年12月20日)で現実逃避しがちであった林は、「肉親から遠く離れて初めて最も身近にその存在を感じ」(1943年5月26日)、シンガポールを経てビルマの戦地までともにした見習士官仲間7人と別れることになると、
「長く一緒に生活すると、相互に好意や尊敬の念を有たないにしても、別離の淋しさは感じ合ふ。長く生活を俱にして来てその存在が知らず知らずの中に私達の身内に食ひ入ってゐるのだ」(同年7月10日)と、孤独を深めた。
休憩なしで12時間働く
日記のなかで、「何処に於ても同じであらうが益益孤独の淋しさを味はねばならない。しかし常に理性的人間に終始しやう」(1943年6月29日)、「如何なる環境に於いても自己を見失はず、個人意識、個人の権威を守って行くこと、同時に他人を対等の人間として遇すること」(同年8月20日)と自らを律したかと思えば、「私は夜が一番好きである――夜私は全く孤独であるから。南の夕は良い。草原に椅子を持出して暮行く空に次次と現れて来る星を見乍ら淋しさに身を浸す時、私は全く自分一人の世界を感ずる」(同年7月11日)、「孤独は楽しむべし」(同年7月30日)とも述べており、彼の自己の揺らぎを垣間見ることが出来る。
「戦争といふ学問とは縁遠い環境に身を置き、虚無主義と享楽主義とが根強く心に拡がってゐる。それが酒を飲んでは外に出て精神を鈍くする」(1944年3月30日)と、戦地で虚無と享楽の間を行き来していたが、1944年4月にラングーンの緬甸方面軍(森集団)司令部参謀部第一課に配属されると生活が一変し、「実に忙しいところで、朝の九時から晩の九時迄ブッ通しで、それに夜中に起きて、電報を整理しなければならない。全く自分の存在等、何処かに失くなって了ふ」(1944年4月21日)という有様だった。