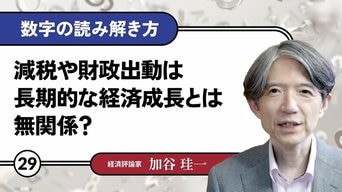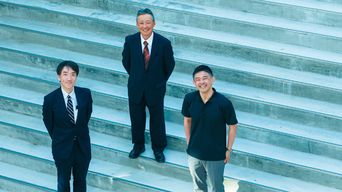※本稿は、井上裕『稲盛和夫と二宮尊徳 稀代の経営者は「努力の天才」から何を学んだか』(日経BP)の一部を再編集したものです。
海水をドラム缶で炊いて作った塩を売り歩いた
稲盛が最初に「ど真剣」に生きたのは一家が闇市で生き延びた戦後しばらくの頃だろう。
小柄で華奢な母・キミが稲盛も驚く気丈さを発揮し、闇市で仕入れた古着と村で買った食糧の物々交換で一家を支えていたのは(本書で)前述の通りだ。母だけを働かせるわけにはいかない。中学生の稲盛も父や兄と一緒に作った焼酎を闇市でさばいたり、海水をドラム缶で炊いて作った塩を売り歩いたり、自分にできることをやった。物資統制下、誰もが今日を生き延びるのに必死で闘っていた時代だった。
稲盛は後に自家製の焼酎や塩は品質に優れ、よく売れたと冗談交じりに自慢しているが、それは定かではない。むしろ、ドラム缶をほかの廃材を使って塩の簡易製造装置に組み上げたり、焼酎造りの温度管理を徹底したりするところは、稲盛が子どもの頃から技術者向きだったことを彷彿とさせ、面白い。
一家は終戦の3年後、疎開地の小山田から市内の薬師町に戻る。稲盛は高校進学を希望するが、父・畩市の猛反対に遭う。
それもそうだ。戦前、羽振りのいい頃は衣装持ちだったキミの着物も、売り尽くしてもはやない。一家挙げての闇市での商売も闇市自体がすでに廃れ始めており、家計に余裕はない。長男はなんとか高校に行かせたが、次男のお前は働いて家計を助けてもらいたいというのが、畩市の本音だった。
「高校へ行きたい」の一点張りで進学
ここで稲盛は「ごてやん」ぶりを発揮する。「高校へ行きたい」の一点張りで、平手打ちに遭っても、家の外に放り出されても初志を曲げない。結局、畩市が折れて、天保山に残っていたわずかな土地を売り、学費に充てた。
人の人生には譲れない分岐点がある。ここで稲盛が折れていたら、その後の稲盛の人生は相当変わっていただろう。進学がすべてではない。だが、その後、稲盛が鹿児島大学でセラミックスの研究に没頭し、京セラを起こし、通信自由化に身を投じ、日本航空(JAL)の再建を成功させたことを考えると、ごねて人を困らせる「ごてやん」ここにありと思わずにはいられない。岩をも通す信念。晩年の稲盛の言葉だ。それが中学生、稲盛の未来を救った。
高校に進んだ稲盛は、父に少しでも報いようと紙袋売りの仕事に精を出すようになる。空襲で印刷所を焼かれ、家も失った失意から仕事をしようとしなかった畩市が、ようやく始めたのが紙袋作りの仕事だった。印刷の技術が生きたからだ。キミもそれを手伝った。稲盛は父母が作った紙袋を猛然と売りさばいた。いわば、家族総出での内職だった。