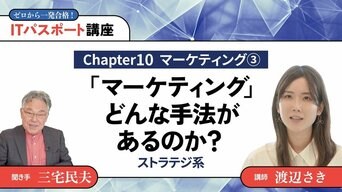※本稿は、塩田雄大『ゆれる日本語、それでもゆるがない日本語 NHK調査でわかった日本語のいま』(世界文化社)の一部を再編集したものです。
カレーの「ルー」は何を指すのか
A カレーの「ルー」というのは、固形や粉末の「カレーのもと」のことを指すことばです。料理として出来上がっている「カレーの汁(=ご飯にかかっている部分)」のことを「ルー」と言うのは、本来はあやまりだと言われています。ですが、この用法は若い年代を中心にかなり広まってきており、社会的にも認められる段階になっているのかもしれません。
「ルー(roux)」というのは小麦粉とバターを加熱しながらまぜあわせたものですが、もともとフランス語で「赤茶色の」という意味です。赤茶色になるように火を通したから、このように呼ばれたのでしょう。とろみがあり、シチューなどにも使われます。
日本式のカレーを作る場合、戦前は各家庭で小麦粉を炒めてそこにカレー粉を加えていました。この手間を省くために、最初からカレー粉と「ルー」を合わせた商品が開発されたのです。これが、カレーの「ルー」です。
「ご飯にかかっている部分」の呼び方は…
では、あの「ご飯にかかっている部分」のことは、何と呼べばよいのでしょうか。かつて軍隊では「辛味入汁掛飯」と呼ばれた時期があることからもわかるように、むかしは「汁」ととらえられていたようです。
しかし、いまの日本人の感覚では「汁」と呼ぶにはあまりに「とろり」としすぎているのではないでしょうか。「(カレー)ソース」という言い方もありますが、ご飯の上にあのように大量にかかっているものを「ソース」とは呼びにくい気持ちもあります。
「カレー」だけだと、ライスが添えられたものなのかどうか、あいまいです。
結局、適当な呼び名がないので、「ルー」ということばがその役を務めるようになったのだと思います。もともとのフランス語にはない使い方ですが、日本語になじんだ外来語の用法として、認めてもよさそうです。
インターネット上でのアンケートでは、「ルー」ということばは「カレーのもと」と「ご飯にかかっている部分」の両方とも指すことができるという人が、特に若い人の間では主流になっていました。
なお、放送では「ルウ」ではなく「ルー」と書くことになっています(次の項をご覧ください)。
カレーは若者に人気のメニューですが、50代のぼくも大好きです。食後はいつも、カレー臭に気をつけています。